EQ=心の知能指数
Lesson1の学習で、マインドフルネスがもたらす効果の一つとして、「EQを高められる」ということを学びました。
今回のLesson2ではこのEQについて、より詳しく学んでいきましょう。

EQの定義
EQとは、「Emotional Intelligence Quotient」の略です。
日本語では、「心の知能指数」「感情知能指数」などと訳されます。
IQ(知能指数)は、遺伝的な要素が強く、生まれつき決まっているのに対し、EQは学び、トレーニングすることで高めることができるという特徴があります。
EQの考え方は、アメリカで始まりました。
EQの基本的な枠組みを最初に発表したのは、ピーター・サロヴェイ博士とジョン・D・メイヤー博士です。
1990年、二人の博士はEQを次のように定義しました。
自分自身と他人の気持ちや情動をモニターし、見分け、その情報を使って自分の思考や行動を導く能力
その後、アメリカの心理学者であるダニエル・ゴールマン博士の著書『EQ – こころの知能指数』が世界的に大ベストセラーとなり、「EQ」という言葉が社会に浸透しました。
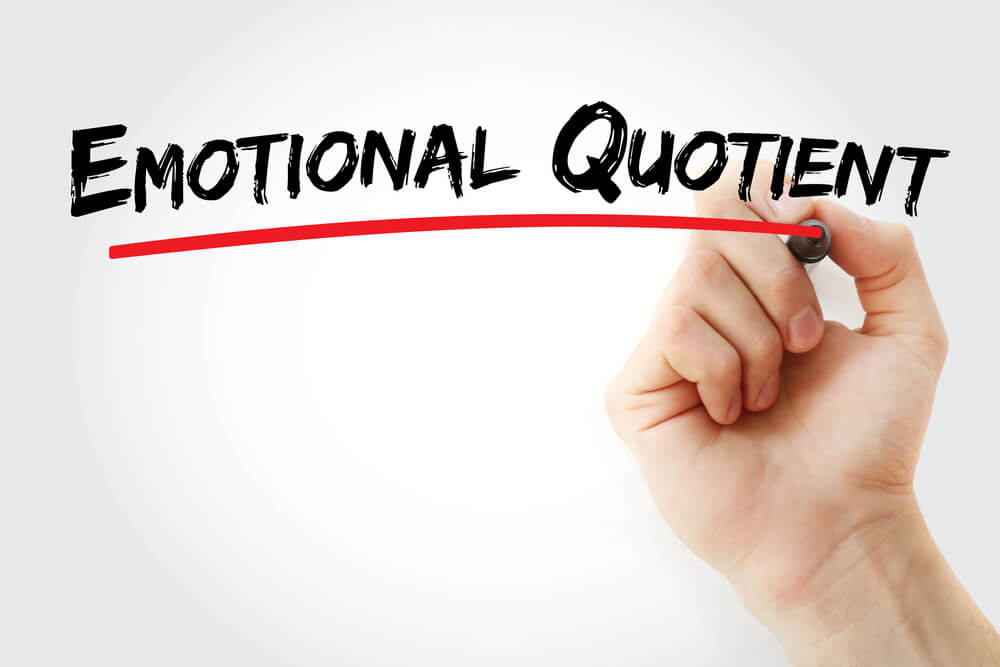
ゴールマン博士は、EQの基本的定義を5つの領域に分類して説明しています。
1.自己の情動を知ること
自分の感情を認識する能力です。
自分の感情がわからない人なんていないのでは?と思う人もいるかもしれませんが、よく思い出してみてください。
「自分の気持ちに後から気がついた」という経験は誰にでもあるはずです。
この能力は、自分が抱いている感情を現在進行形で認識できる能力で、EQでもっとも大切で基本的なことです。
2.自己の感情を制御すること
いつも自分の感情を適切な状態にしておく能力です。
生きていると良い感情のときも不快な感情のときもあります。
特定の感情が強く出たり、それが長期間になると病的な状態になってしまいます。
どんなときも自分の感情のバランスを取り、コントロールすることが大切なのです。
3.自己の動機づけをすること
目標に向かってモチベーションを上げることができる能力です。
また、快楽や衝動を抑えることができるセルフ・コントロール能力でもあります。
持って生まれた才能を生かせるかどうかは
「どんなことがあってもモチベーションを高く保持できるかどうか」という、
この能力にかかっているのです。
4.他人の感情を知ること
人に共感でき、人の感情や気持ちを読み取る能力です。
この能力は、仕事や人間関係、結婚や子育てなど、人生のあらゆる場面で必要になります。
人の感情は、声の調子、身ぶり、表情など非言語的なヒントから読み取ることが多いですが、この能力が高い人は、人から好かれ、外交的であることがわかっています。
5.人間関係を円滑にすること
人と上手に付き合うための社会的能力です。
この能力は、「自分の感情を制御する能力」と、「他人の感情を知ることができる能力」の上に成り立ちます。
社会的能力が低いと、対人関係でつまずくことが多いのですが、
知能的にはとても優秀な人であっても、人から好かれない場合があるのは、この能力が欠けているためなのです。
1〜3は自己の内省的な知能、4〜5は対人的な知能になります。
人によって分野ごとに能力の差はありますが、正しく矯正すれば能力を向上させることができるとゴールマン博士は述べています。