組織に必要なマインドフルネス
マインドフルネスは仏教にルーツをもつ考え方ですが、現在は一般化され、宗教や国境を越えて世界中に広がり、アメリカの企業や組織を中心に導入されてきました。
近年では、日本の多くの企業も導入しています。
一見すると、決められたタスクをこなし、個人の目標を達成し、
さらに革新的なアイデアが求められる企業において、
マインドフルネスは関係がないように思えるでしょう。
それではなぜ、今、組織はマインドフルネスを求めているのでしょうか。
その理由についてまずは考えていきます。

科学的な裏づけと実績による信頼
世界に名だたる企業がマインドフルネスを取り入れる理由の一つは、マインドフルネスの効果に科学的根拠があるためです。
脳には大脳辺縁系の一部である「海馬」という部分があります。
海馬は、短期記憶に関係する部分ですが、日常的なできごとなどはこの海馬に集められます。
そのため、仕事の処理能力などにも影響すると考えられます。
しかし、海馬はストレスに脆弱という面があります。
慢性的なストレスがあると、萎縮してしまうのです。
しかし、ある実験の報告によると、継続してマインドフルネス瞑想を実践することにより、この海馬の厚みが増すことがわかりました。
海馬の厚みが増すと、その機能が向上します。
また、脳には「扁桃体」という部分がありますが、この扁桃体は不安や恐怖を感じると活性化します。
扁桃体が活発になるとカッと怒りがこみ上げたりパニックになったりします。
怒りや不安があるときの脳を観察すると、
扁桃体と前頭葉前部の右半分が活発になっているのがわかります。
前頭葉の右半分が活発になるとネガティブになり、前頭葉の左半分が活発になるとポジティブになると言われています。
これを「扁桃体ハイジャック」と呼びます。
扁桃体ハイジャックが起こると、意識がネガティブな方に向いてしまうのです。
この扁桃体の活性化も、マインドフルネス瞑想を継続することにより反応がある程度抑えられるようになるということがわかっています。
つまり、感情のコントロールができるようになるのです。
マインドフルネスは多くの人が実践し、「効果がある」と実証されてはいるものの、
こうした科学的裏付けがあるからこそ、世界の大企業が研修を取り入れ実践しているというわけなのです。
EQを高めることができる
EQとは、心の知能指数のことです。
Lesson2-3 でも取り上げましたが、組織のリーダーは、
トップに近ければ近いほどEQが高いことがわかっています。
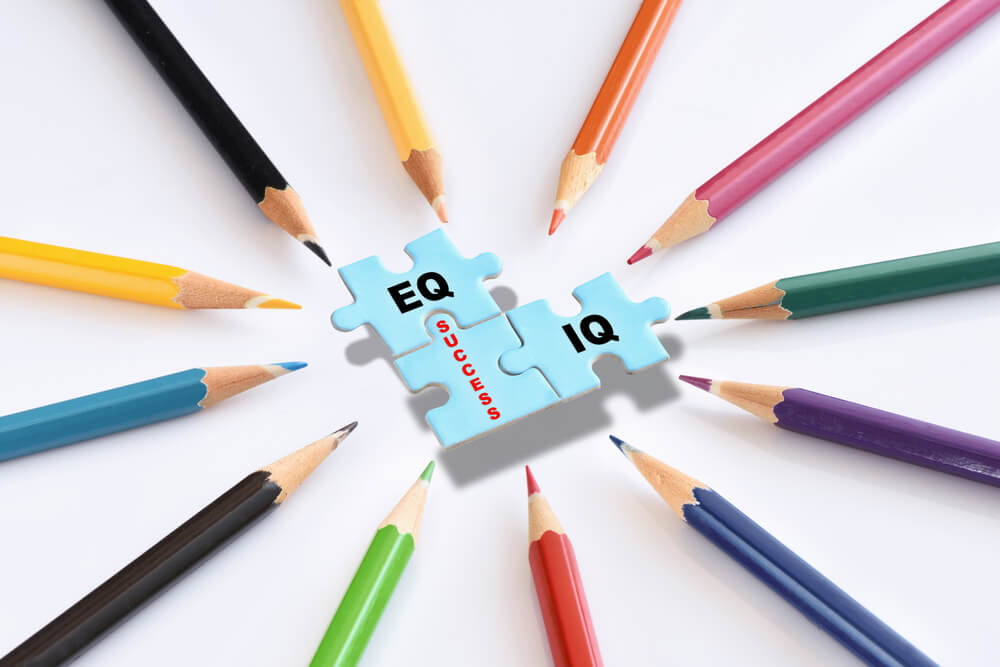
EQには5つの領域があることを学びましたが、覚えているでしょうか。
組織の中で目標を達成するのに必要な領域は「3.自己の動機づけをすること」です。
また、組織のリーダーに欠かせないのは「4.他人の感情を知ること」「5.人間関係を円滑にすること」です。
3〜5のどれも、「1.自己の情動を知ること」「2.自己の感情を制御すること」ができるようになってはじめて成り立つことです。
自己認識(自分を知ること)ができなければ自己管理はできませんし、ましてや人の感情を知ることもできません。
この自己認識力は、マインドフルネス瞑想で高めることができます。
つまり、マインドフルネスを身につけることで、最終的にはEQが高まるのです。
さらに、人の感情は伝染しやすく、特に組織においては、リーダーの感情はグループのメンバーに伝染します。
つまりEQが高いリーダーのグループは、グループ全体に良い影響を与えるということになります。
これらの理由から、多くの組織ではマインドフルネスが導入されているのです。
次のセクションでは、「マインドフルネスが組織にもたらす効果」について学びましょう。